<全人代>日本人経済学者 2025年の中国経済は「"AI+"とイノベーションで持続可能性の向上が見込める」と評価
第14期全国人民代表大会第3回会議が11日午後、「政府活動報告」を採択して閉幕しました。今年の「政府活動報告」では、大規模言語モデルの広範な応用に対する支援や、インテリジェント・コネクテッド新エネルギー車、人工知能(AI)を搭載したスマートフォンやコンピューター、エンボディドAI(身体性を備えたAI)などの発展を大きく推進し、デジタル経済のイノベーションの活力を引き出すことが強調されています。
こうした中国政府の方向性について、中国のデジタル経済やイノベーションを研究する北京在住の日本人学者、西村友作氏(対外経済貿易大学教授)はポジティプな評価を行いました。

西村氏は、今年の中国の政府活動報告について、昨年に続いてAI技術を経済社会のさまざまな領域に融合させる「AI+(プラス)」行動を提唱していることに注目し、「実体経済のイノベーションを促進し、既存産業の新たな発展を追求するものだ」と指摘しました。また、「特に、製造業やサービス業におけるAIの活用は、生産性の向上と新たなビジネスモデルの創出に寄与するだろう」と期待を示しました。
2025年の幕開けとともに、中国発の大規模言語モデル「ディープシーク」や汎用AIエージェント「マヌス」などが立て続けに発表され、世界で注目を集めています。西村氏は、「これらは、中国が『自立自強』を掲げ、科学技術の自主開発を推進してきた成果の一例」との見方を示しました。
低価格、高性能、オープンソースを特徴とする「ディープシーク」が登場したことの意義については、「ディープシークがオープンソースで技術を提供したことを受け、他の企業も技術情報の公開に踏み切っている。これにより、中国の生成AIの発展がさらに加速し、企業にとっては低コストで高品質な生成AIを利用できる環境が整いつつある」と指摘し、とりわけ、「製造業、医療、教育など分野でのAI活用が期待される」と展望しました。
さらに、中国の経済政策の基本方針である「先立後破(先に確立し、後に破壊する)」にも言及し、西村氏は、「新たな成長産業を育成しつつ、不動産への依存度を低下させることを目指している。これにより、経済の持続可能性を高めることが可能となるだろう」との見方を示しました。(取材:王小燕 校正:MI)
4月7日ニュース
00:00 /
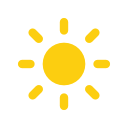 25°C
25°C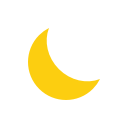 14°C
14°C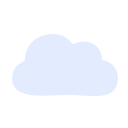 27°C
27°C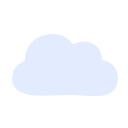 20°C
20°C



 サイト内検索
サイト内検索




 京公网安备 11010502050052号
京公网安备 11010502050052号